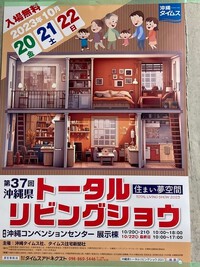2013年12月22日
まちま〜い 首里三箇〜泡盛と王朝文化を育んだ城下町
みなさん体調管理は万全ですか?
12月21日(土)強い北風の吹く中 今回はガイドさんと那覇市首里の三箇(赤田、崎山、鳥堀)をねり歩いていろいろな話を聞くことができました。琉球王国時代、唯一泡盛の製造が許されていた地域で豊富で美味しい水に恵まれた城下町を地元出身の池原がレポート致します。
今回はガイドさんと那覇市首里の三箇(赤田、崎山、鳥堀)をねり歩いていろいろな話を聞くことができました。琉球王国時代、唯一泡盛の製造が許されていた地域で豊富で美味しい水に恵まれた城下町を地元出身の池原がレポート致します。
今回は主に下記のようなポイントをまわりました。見所盛りだくさんの内容となっていますよ。
①聞得大君後殿跡 ②咲元酒造合資会社 ③首里殿内跡 ④有限会社識名酒造
⑤石垣(ボーンター積み) ⑥御茶屋御殿跡 ⑦雨乞御嶽 ⑧崎山御嶽 ⑨首里城継世門 10瑞泉酒造株式会社

①首里中学校前
聞得大君加那志の住居と神殿跡。ここで国王の長寿、琉球王国の繁栄、五穀豊穣、航海安全などを祈願したそうです。

②咲元の咲は方言の酒(サキ) 泡盛、元は元祖、泡盛の原点の意味を込めているとのことです。

試飲もできちゃいます
ここから、赤田すんどぅんち(通りの名前)をまっすぐ進み、暫くして進行方向左手に赤田町倶楽部(公民館)があります。ここはかつて首里殿内跡でした。

③首里殿内跡
首里大あむしられの住居と神殿跡で、中には「赤田みるくウンケー」の面と胴が奉納されているそうです。

旧暦7月16日に弥勒神(ミロクジン)が町を練り歩く「ミルクウンケー」という行事が古くから伝えられています。
さらに道は続きます。たまに素敵な標識や

おもしろいシーサーを見つけたりして

そうこうしているうちに私のお気に入り泡盛のひとつ 「時雨」を製造している酒造所、有限会社識名酒造に到着しました。ここでガイドさんが素敵な詩を紹介してくれました。「浜までは海女も蓑着る時雨かな」

④現存する最古の古酒 150年 と130年ものを家宝として保有し、泡盛ファンの垂涎の的となっております。
時雨はあまりでまわっていませんが風味豊かで美味しいのでもし機会があればお試しあれ。
赤田市場跡を通り、「ボーンター積み」と呼ばれる上部が丸くなっている独特な石垣のある路地を散策し首里カトリック教会へ到着。高台ということで風の強さと寒さがピークを迎えます。

御茶屋御殿跡地から望む風景

⑥御茶屋御殿跡
この一帯は琉球王家の別邸兼迎賓館で冊封使などの国賓を歓待した場所で、文化の伝道として、琉球文化発祥の地の役割もになっていたそうです。景観も素晴らしい。


御茶屋御殿石造獅子。御殿を火災やその他の災厄から守るために1677年に製作され、火難をもたらすと考えられていた八重瀬岳に向かって設置されていました。

⑦雨乞御嶽
干ばつの際は、国王が自ら神女や家臣たちを率いて、雨乞いの祈願を行っていたそうです
崎山御嶽を通り過ぎて首里城継世門へ

⑨首里城の東南部に位置する門でかつては首里城一美しいと言われていたそう。国王が死去した後、世子はこの門をくぐり内郭の美福門を経て御内原の世誇殿で、王位継承を行ったことに名前の由来があるそうです。
最終地点、瑞泉酒造株式会社に到着。那覇市の景観賞もとったといわれるこの通り、私もお気に入りです。

10瑞泉酒造株式会社
こちらでは泡盛の製造工程をテレビで観てから実際に工場の中を説明を聞きながら見ていきました。
材料はタイ米と黒麹菌と水。それらを合わせて発酵。2週間ほどかけて「もろみ」をつくる。その時のアルコール度数は18度。
蒸留されて50度のものができあがるのでそれぞれの度数までうすめられ貯蔵しまろやかにする。貯蔵するものは樽、瓶、ステンレスがあるが素材によって風味が変わるとのこと。

興味深いですね。ということでお楽しみ試飲会

三年以上熟成された泡盛をくーす(古酒)と呼びますが、今回は10年ものを試飲させていただきました。
非常にまろやかで度数の高さやキツさを一切感じさせない美味なくーすでした。瑞泉酒造さん、ありがとうございました。
先ほどまでの寒さや疲れはどこえやら。。。
長時間、寒い中皆様お疲れ様でした。そして私たちの安全を気遣いながらガイドしていただいた真栄田さん本当にありがとうございました。
今回参加されなかった方も一度は参加されることをお勧めします。
長いレポートお付き合いありがとうございました。
12月21日(土)強い北風の吹く中
 今回はガイドさんと那覇市首里の三箇(赤田、崎山、鳥堀)をねり歩いていろいろな話を聞くことができました。琉球王国時代、唯一泡盛の製造が許されていた地域で豊富で美味しい水に恵まれた城下町を地元出身の池原がレポート致します。
今回はガイドさんと那覇市首里の三箇(赤田、崎山、鳥堀)をねり歩いていろいろな話を聞くことができました。琉球王国時代、唯一泡盛の製造が許されていた地域で豊富で美味しい水に恵まれた城下町を地元出身の池原がレポート致します。今回は主に下記のようなポイントをまわりました。見所盛りだくさんの内容となっていますよ。
①聞得大君後殿跡 ②咲元酒造合資会社 ③首里殿内跡 ④有限会社識名酒造
⑤石垣(ボーンター積み) ⑥御茶屋御殿跡 ⑦雨乞御嶽 ⑧崎山御嶽 ⑨首里城継世門 10瑞泉酒造株式会社

①首里中学校前
聞得大君加那志の住居と神殿跡。ここで国王の長寿、琉球王国の繁栄、五穀豊穣、航海安全などを祈願したそうです。

②咲元の咲は方言の酒(サキ) 泡盛、元は元祖、泡盛の原点の意味を込めているとのことです。

試飲もできちゃいます

ここから、赤田すんどぅんち(通りの名前)をまっすぐ進み、暫くして進行方向左手に赤田町倶楽部(公民館)があります。ここはかつて首里殿内跡でした。

③首里殿内跡
首里大あむしられの住居と神殿跡で、中には「赤田みるくウンケー」の面と胴が奉納されているそうです。

旧暦7月16日に弥勒神(ミロクジン)が町を練り歩く「ミルクウンケー」という行事が古くから伝えられています。
さらに道は続きます。たまに素敵な標識や

おもしろいシーサーを見つけたりして

そうこうしているうちに私のお気に入り泡盛のひとつ 「時雨」を製造している酒造所、有限会社識名酒造に到着しました。ここでガイドさんが素敵な詩を紹介してくれました。「浜までは海女も蓑着る時雨かな」

④現存する最古の古酒 150年 と130年ものを家宝として保有し、泡盛ファンの垂涎の的となっております。
時雨はあまりでまわっていませんが風味豊かで美味しいのでもし機会があればお試しあれ。
赤田市場跡を通り、「ボーンター積み」と呼ばれる上部が丸くなっている独特な石垣のある路地を散策し首里カトリック教会へ到着。高台ということで風の強さと寒さがピークを迎えます。

御茶屋御殿跡地から望む風景

⑥御茶屋御殿跡
この一帯は琉球王家の別邸兼迎賓館で冊封使などの国賓を歓待した場所で、文化の伝道として、琉球文化発祥の地の役割もになっていたそうです。景観も素晴らしい。


御茶屋御殿石造獅子。御殿を火災やその他の災厄から守るために1677年に製作され、火難をもたらすと考えられていた八重瀬岳に向かって設置されていました。

⑦雨乞御嶽
干ばつの際は、国王が自ら神女や家臣たちを率いて、雨乞いの祈願を行っていたそうです

崎山御嶽を通り過ぎて首里城継世門へ

⑨首里城の東南部に位置する門でかつては首里城一美しいと言われていたそう。国王が死去した後、世子はこの門をくぐり内郭の美福門を経て御内原の世誇殿で、王位継承を行ったことに名前の由来があるそうです。
最終地点、瑞泉酒造株式会社に到着。那覇市の景観賞もとったといわれるこの通り、私もお気に入りです。

10瑞泉酒造株式会社
こちらでは泡盛の製造工程をテレビで観てから実際に工場の中を説明を聞きながら見ていきました。
材料はタイ米と黒麹菌と水。それらを合わせて発酵。2週間ほどかけて「もろみ」をつくる。その時のアルコール度数は18度。
蒸留されて50度のものができあがるのでそれぞれの度数までうすめられ貯蔵しまろやかにする。貯蔵するものは樽、瓶、ステンレスがあるが素材によって風味が変わるとのこと。

興味深いですね。ということでお楽しみ試飲会


三年以上熟成された泡盛をくーす(古酒)と呼びますが、今回は10年ものを試飲させていただきました。
非常にまろやかで度数の高さやキツさを一切感じさせない美味なくーすでした。瑞泉酒造さん、ありがとうございました。
先ほどまでの寒さや疲れはどこえやら。。。
長時間、寒い中皆様お疲れ様でした。そして私たちの安全を気遣いながらガイドしていただいた真栄田さん本当にありがとうございました。
今回参加されなかった方も一度は参加されることをお勧めします。
長いレポートお付き合いありがとうございました。